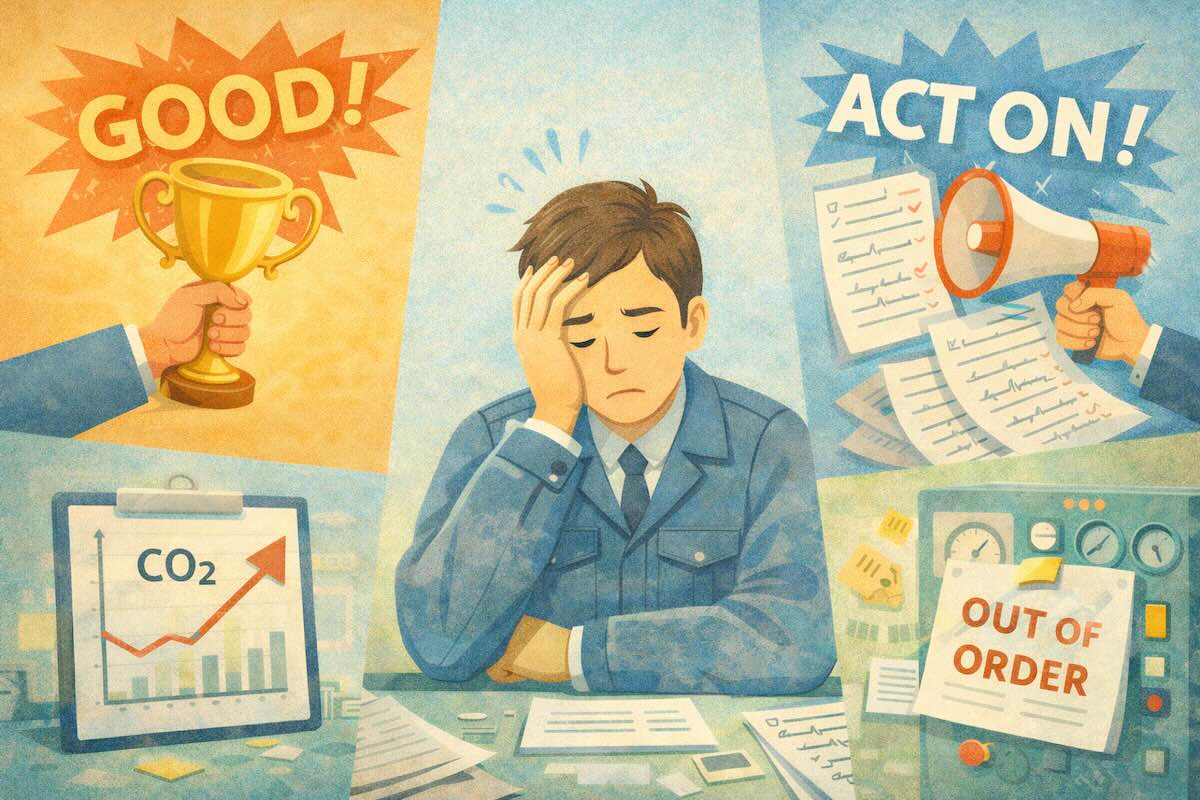脱炭素のキーワードは“見える化” ― エネルギーDXのはじめかた

最近、ニュースや企業サイトで「脱炭素」や「エネルギーDX」という言葉をよく見かけるようになりましたよね。
でも、「うちの工場やオフィスには関係なさそう」と感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、どんな現場でも今日からできることがあるんです。
その第一歩が、“見える化”です。
今日は、脱炭素社会に向けて「エネルギーをどうやってデジタル化し、行動につなげるのか」をお話しします。
🌱 まずは“知ること”から始まる脱炭素
「エネルギーDX」というと、AIやIoTなど難しそうな技術を思い浮かべがちですが、
本質は「データを使ってムダを減らすこと」。
どこで、いつ、どれくらいのエネルギーを使っているのかを“知る”ことからすべてが始まります。
たとえば、照明や空調、製造設備などがどの時間帯にどれだけ電力を使っているのかを把握できれば、
無駄な稼働を抑えたり、運転時間を調整したりといった改善につながります。
まずは感覚ではなくデータで把握すること。
これが脱炭素への最初の一歩です。
⚙️ “見える化”がもたらす気づきと行動変化
データを“見える化”すると、人の行動が変わるのを感じます。
設備の稼働データをリアルタイムで確認できるようになると、
「この時間帯は思ったより電力を使っているな」といった具体的な気づきが得られます。
ある製造現場では、IoTによるエネルギー計測を始めたことで、
不要な稼働時間や電力の使いすぎが可視化され、結果的に社員全体の省エネ意識が高まったという報告もあります。
数値で現状を見えるようにするだけでも、自然と行動改善につながるんです。
💡 小さく始めて続けることが大切
エネルギーDXを始める際に、最初から大掛かりなシステムを導入する必要はありません。
小さな一歩からで大丈夫です。
たとえば、主要設備の電力計測だけを始めてみる。
あるいは、工場全体の使用量を1日単位でグラフ化する。
それだけでも、どの工程でエネルギーが多く使われているかが見えてきます。
こうした小さな「見える化の積み重ね」が、次の改善策を生み出します。
データが蓄積されるほど、AIによる分析や自動制御など、より高度な省エネ施策にも発展させやすくなります。
💡 オレンジボックスのエネルギーDX支援
オレンジボックスでは、IoTとAIを活用したエネルギーの見える化ソリューションを提供しています。
工場やビルの電力・設備データをリアルタイムで収集し、
クラウド上のダッシュボードで一目で確認できるようにすることで、
「どこにムダがあるか」を明確に把握できます。
さらに、AIが分析結果をもとに異常傾向を検知したり、
最適な稼働パターンを提案したりする機能も備えています。
中小規模の工場でも導入しやすい構成を意識し、
“まずは一部から試してみる”という段階的なアプローチにも対応しています。
🌏 見える化は脱炭素への確かな一歩
脱炭素は、特別な取り組みではなく、日常の中から始められます。
まずはエネルギーの使い方を見える化し、現状を“知る”こと。
それが改善の出発点であり、持続的な省エネの土台になります。
データが見えることで意識が変わり、行動が変わる。
そして、その小さな積み重ねが未来の地球を少しずつ変えていくのだと思います。